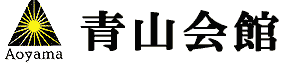
諸行無常といって、生あるものは必ず滅びる、ということは観念上では判っていながらも、人は他者の死を通じて間接的にしか体験できません。
人は他者の死に直面して、やがては死が、わが身に襲ってくることを知るが、死がいつどのような形で訪れてくるのかは皆目わかりません。
死は直接追体験できないことから、人は他者の死を通して自分の死を見つめることになります。
死を考え、その意味を問うことは、そのまま自己の生を考えることに相違ありません。
人の死を悼んで人々が集まり営まれる葬儀は、集まる人々にいのちの大切さ、生あるものは必ず死ぬべき存在であることを知らしめます。
そこで人々は死が周囲の人々に悲嘆をもたらすほどの大きな事実であることに直面し、体験的に生の大切さを知り、死が決して終わりや無を来すものではない、ということを学びとります。
生は絶えず死の恐怖におののき、死は生への刺激となります。
宗教信仰とは、人が死と生とを、表裏の関係で主体的に考えることから、導き出されるのであり、人の死は単に個人の現象にとどまらず、社会的・文化的な意味が担われてきたのだといえます。
人間は、生物的な存在であるだけではなく、社会的な存在としてもこの世界に生きています。
つまり人間は、その人を知っている多くの人々の、心の中にも生きている、ということであるならば、ひとり肉体の死をもって、ある人の全的な死・消滅とはみなせないのです。
こうして、生を意味付けるためにも、死を超えるさまざまな観念体系(霊魂観、他界観を含めた死生観)が作り上げられ、それが具現的に行為化されたものが死者に対する儀礼、いわゆる葬儀・追善供養だと考えることができます。
当該民族がもつ死生観が、葬儀式に凝集されているが故に、葬儀を問うことは人の生きざま死にざまの宗教的意味だけでなく、その文化的・社会的意味を問うことにもなるといえます。
このような葬儀の役割をまとめると、次のようになります。
社会的役割(社会的な処理)
社会にその人の死を告知する、死亡届、戸籍、相続など
物理的役割(遺体の処理)
土葬、火葬など
文化・宗教的役割(霊の処理)
死者の霊を慰め、「この世」から「あの世」へ送り出す、あの世での幸せを祈る
心理的役割(悲嘆の処理)
悲しみにある人々の心に寄り添い、慰める
社会心理的役割(さまざまな感情の処理)
崇り、死霊への恐怖感の緩和
教育的役割
いのちの大切さ、生あるものは必ず死ぬべき存在であることを知らしめる
葬送儀礼の特徴は、儀礼対象が死者であり、生者が死者のために営むところにあり、生者の死者に対する態度によって生者・死者・死霊の三要素が関連しあって、さまざまな死生観・習俗が生み出されています。
生者が死者に対して抱く情緒反応には、死者に対する愛惜の念と腐敗していく屍に対する恐怖・嫌悪感という、相矛盾した情緒の併存が指摘されています。
例えば、葬法のなかで、ミイラにして永久に保存するという類は、再生観念に裏付けられた愛惜の念の高じた一方向であり、他方は、一刻も早く死体との関係を断ち切りたいという心的傾向をもち、その極端な葬法が火葬であるということができます。
しかし、その根底には死者が生前いかに敬愛されていても、腐敗していく死体は嫌悪感と死霊への恐怖をまきおこすのであり、死者が怖れられる存在であることは、人類に共通して認められると考えられます
日本では、死者には生者を死の世界に引きずり込もうとする力があると考えられてきました。
古事記・日本書紀でのイザナギ・イザナミの神話にみられるように、イザナギが強い禁止を侵したために、イザナミの腐敗した肉体という、原始的で恐ろしい死を目の当たりにし、死の穢れをもって帰ったイザナギが海水で禊(みそぎ)をしたことは、お葬式での"清め塩"に繋がっています。
日本の葬法は、すでに縄文時代にも埋葬が行われていたことが考古学上立証されているように土葬が基本形であったことはよく知られています。
日本において仏教は、その定着化の過程のなかで、在来の民間信仰に意味付けを与えて、積極的に仏教体系のなかに組み入れてきたといえます。
葬送儀礼は、中世以降、積極的に仏僧が葬儀に関与したために、仏教葬が基本的葬法となり、先祖供養の習俗が一般化して今日に至っています。
仏教の影響による火葬の採用は、土葬に特徴的な死者・死霊への恐怖を和らげることに力を貸すこととなります。
火葬の宗教的意味は、火のもつは払浄力にあります。
なにものをも焼き尽くす火は死霊への恐怖も穢れも払拭する力を持つものであり、霊の昇天への手段であったのです。
遺骸の白骨化は、死の穢れを払拭した象徴、いわゆる成仏の表象でした。
火葬の導入普及は、短時間の間(歴代天皇の風葬に見られる葬法は、遺体を十分に骨化させるほどの時間が必要だった)に遺骸の白骨化を可能にさせ、死者・死霊の恐怖を和らげて愛惜の念の高揚に力を貸したのです。
仏教の影響は火葬の普及を促し、祖先崇拝を構築するのですが、屍から遊離した死霊は、火葬による焼却で遺骨と化すことによって、すでに穢を去って清められた象徴として遺骨は文字通り先祖の霊の縁(よすが)と生まれ変わるのです。
死霊は個性をもち、死穢をもっています。
子孫がこの死霊を祀ることによって、死霊は個性を失い浄化されて行きます。
また死霊から祖霊への展開は人間の成長段階の推移と重ね合せて考えることができます。
(汚れた)赤ちゃんの時期は親の保護が必要です。
この時期は死霊も汚れた存在であり、親の保護をうけるように、生者からの供養をうけなければ、次の段階には進めないのです。
少年期・青年期は親の保護下にあり、やがて成人となり、結婚して子供をもうければ今度は保護者の立場に変わります。
祖霊は現実に生きている人間の延長としてとらえられたのです。
このような生者と死者のサイクルのなかで、生者は絶えず、祖霊・祖先の守護の下に現在ある自己を位置付け、やがて死すれば祖先・祖霊となって、草葉の陰から子孫の行く末を見守ろうとするなかに、日本人は生き死にを考えてきたのです。
まさに生のなかに死をみつめ、死のなかに生を感ずる循環的な死生観が日本の祖先崇拝の精神風土に根付いていったのです。
5 現代お葬式事情
昨今、価値観の多様化、個人主義、核家族化の進行、地域社会の崩壊とともにお葬式が、地域共同体主体から家族主体に変わってきました。
かつては、地域社会の慣習を基本に葬儀を進め、祭壇の大きさでその弔う気持ちを表わしていたが、今は、「故人らしさ」「その人らしさ」を何らか表現することにより、故人への想いの深さを測っているようです。
さらにこれから、高齢者世帯の増加、小子化、非婚化などで、お葬式の主体たる家族が変化していくならば、お葬式の多様化は、ますます強まると考えられます。
「お葬式は遺された者が死者を弔うために行うもの」というのが、過去からこれまでのお葬式の概念でしたが、「お葬式は自分の死に際して、自分がこの世と別れるために行われるもの」、「自分らしく生きて、自分らしく死ぬ」という新しい概念が、近年、広まってきています。
同時に「弔いは自由ではないか」とする主張とともに、従来のお葬式の様式を否定し、自分たちなりの新しい様式をもとめる風潮が顕著となってきました。
「お葬式をしない」といった、お葬式に対する批判について、要約してみると
①自分は仏教徒ではないのに、なぜ死んだら仏式で葬儀をあげなくてはいけないのか
・・死生観の多様化、信仰心がない、寺檀制度の薄れ、
②自分は家族や知人だけに見送られたいのに、 なぜ、あまり関係ない人にまで迷惑をかけて大げさに死んでいかなくてはならないのか(地味葬志向)
・・「死や葬儀は個人的なもの」という感覚、社会儀礼的なものへの反発
③生きている者こそ大切なのに、なぜお葬式に巨額のお金をかけなくてはいけないのか(簡素派)
・・「自分のために家族がお金のことで無理して欲しくない」という考え
④死は自分のものなのだから、自分の意志どおりのお葬式をしていいはずなのに、なぜ、世の中の慣習にあわせたお葬式をしなければいけないか(自由派)
・・個人主義、地域社会の崩壊、高齢者の中にも戦後派が登場してきたこと
⑤お葬式は生きている者の世間体を飾るだけのものになっているのではないか。そんなお葬式はしなくていいのではないか
・・現状のお葬式が「故人のため」とはなっていない、とする考え
といったところですが、実は「お葬式をしない」と言っても、その内容はさまざまです。
自分たちが常識的にイメージしている姿のお葬式をしないことがそのような表現となっています。
お葬式をしたくないと考えている人は、お葬式そのものを否定しているのではなくて、現状のお葬式が自分たちの考えるお葬式とは異なるということになります。
しかしながら、自分の考える死のデザインと家族の死に出会った遺族の弔いとは常に一致するとは限りません。
自分の死だけが全てではなく、遺された者にとっての死ということも当然存在します。
一人の死を巡って、周囲のそれぞれがそれぞれの仕方で死を体験しているのです。
お葬式という儀礼は、社会的には「死者を死者として認める」ということであり、死を告知する意味に加えて、死者の尊厳を社会的に承認することを意味しています。
死者が、仮に社会的には無名であったとしても、葬式を営むことは、その死者が生きた人生への尊厳、共感を寄せ、かけがえのない一個の人格、いのちとして尊重して、その死を惜しむ、ことなのです。
おまけ 葬儀の慣習 民間信仰
参考文献
「葬儀概論」 碑文谷 創 著(表現文化社)
「葬儀大事典」 藤井正雄
監修(鎌倉新書)
